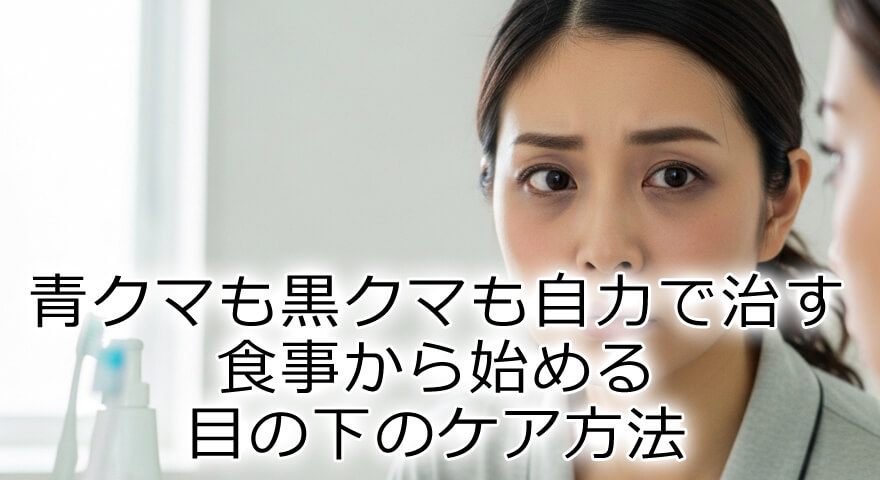朝、鏡をのぞいたときに「なんだか今日は顔が疲れて見えるな」と感じることはありませんか。
それ、実は目の下のクマが原因かもしれません。クマはメイクで隠すこともできますが、自力で改善するためには「体の中から整える」ことが欠かせません。食事は毎日続けられる自然なケアの第一歩です。クマを自力でケアしたい人のために、栄養と食べ物、そして習慣の見直し方を紹介します。
目の下のクマができる原因とは
目の下のクマは種類によって原因が異なります。青クマは血行不良による酸素不足、茶クマは色素沈着や摩擦、黒クマはたるみや目の下のふくらみが影のような見え方が原因です。どのタイプにも共通しているのは、血行不良・栄養・睡眠・ストレスなど、生活のリズムと深く関係しているということです。
目の周りは皮膚が非常に薄く、血管の状態や筋肉の衰えがすぐに表情に出やすい個所のため、体の中から血行を良くし、必要な栄養素をしっかり摂ることが、クマを自力で改善することが大事です。
青クマは血行不良が原因。現代人に増えている“疲れ目クマ”
青クマは、血液の流れが悪くなることで起きる状態です。目の下は特に皮膚が薄く、毛細血管が透けやすい部分です。血行が滞ると、血液が酸素不足の状態になり、色が黒っぽく変化します。薄い皮膚を通してこの血液が見えることで、青いクマのように映ってしまうのです。
青クマになりやすい理由のひとつが眼精疲労です。
スマートフォンやパソコンを長時間眺める生活が続くと、まばたきの回数が減って目の周辺の血流が悪くなり、疲れがたまり続けてしまいます。睡眠不足、不規則な生活、偏った食事、ストレス、冬場の冷えなども血行不良を引き起こす大きな要因です。体調によって青さの濃さが変わるのも、血流状態が日々変化するためです。
青クマのチェック方法は、目の下の皮膚を指で軽く引っ張って、色が薄くなったり、一時的に肌色に近づいたりすれば青クマの可能性が高いです。
黒クマはたるみが原因。影が落ちて黒く見えるタイプ
黒クマは、皮膚のたるみや目の下のふくらみが影のように見えるのが主な原因です。
年齢を重ねるにつれて、目の周りの筋肉(眼輪筋)や皮膚のハリを支えるコラーゲン・エラスチンが少しずつ減っていき、皮膚がたるんだり、膨らみができたりして目の下に影が生まれやすくなります。
黒クマか確かめるには、上を向いたときにクマが薄くなるか、指で皮膚を軽く引っ張って影が消えるかをチェックすると判断できます。影が動いて薄くなるなら、黒クマの可能性があります。
青クマと黒クマは原因が違うから、ケア方法も変える必要がある
どちらも「目元が疲れて見える」という点では同じですが、原因は全く異なります。青クマは血行不良の改善が重要で、体内のめぐりを良くする生活習慣が大切です。黒クマはたるみが原因のため、筋肉の衰えや肌のハリ不足をケアしていく必要があります。
どちらのタイプも、体の内側からのケア—栄養、睡眠、ストレスのコントロール—が土台となります。毎日の生活の中で小さな習慣を取り入れることで、クマの見え方は着実に変わっていきます。
食事で目の下のクマを改善する
体の状態は、毎日の食生活で作られます。目の下のクマも例外ではありません。
偏った食事や過度なダイエット、冷たい飲み物の摂りすぎは血流を滞らせ、目元のくすみや疲れが残る原因になります。目の下のクマ対策の食事で大切なのは、血液の質を良くしてめぐりを整えることと、肌の再生を助ける栄養素を補うことです。
目の下のクマの色に合わせて“食べて整える”
- 青クマには「血を補う食材」
- 黒クマには「筋肉とハリを支える栄養」
それぞれのタイプを見極め、食事から整えていくことで、自然で健康的な明るい目元に近づくことができます。今日の献立にほんの少しの意識を加えるだけで、目元の印象は確実に変わります。ビタミンとたんぱく質の力で、内側から「めぐり」と「ハリ」を取り戻しましょう。
青クマに効果的な食事と栄養素
青クマは、血行不良や酸素不足によって血液中のヘモグロビンがうまく循環せず、皮膚の下に透けて見えることで起こります。冷え性や睡眠不足、鉄分の不足が関係しており、体の「めぐり」を整えることが何よりも大切です。
注目したいのは鉄分。
鉄分は血液の主成分であり、酸素を全身に運ぶヘモグロビンを作るために欠かせません。不足すると目元の血流が滞り、皮膚の下が青黒く見えるようになります。
鉄分は、レバー・赤身の肉・マグロ・カツオ・あさり・ひじき・ほうれん草などに多く含まれます。また、鉄分は単体では吸収されにくいため、ビタミンCを一緒に摂るのがおすすめです。たとえば「ほうれん草のおひたしにレモンを絞る」「牛肉のソテーにブロッコリーを添える」など、台所で簡単にできる組み合わせを意識しましょう。
次にビタミンE。
血管を広げて血のめぐりを良くする働きがあり、冷えやストレスで血行が悪くなりやすい人にぴったりです。ナッツ類、アボカド、かぼちゃ、オリーブオイルなどに豊富に含まれています。とくに更年期世代の女性はホルモンの影響で血行が落ちやすくなるため、積極的に摂ると良いでしょう。
ビタミンB群も大切です。
ビタミンBは、疲労を軽減し、代謝を助けて血液の流れをスムーズにします。豚肉、卵、納豆、玄米などに含まれ、日常的に取り入れやすい食材ばかりです。
これらを意識した献立を週に数回でも取り入れると、青クマが少しずつ薄くなり、目元の色味が明るく感じられるような効果が期待できます。食事だけでなく、温かい飲み物を選んで体を冷やさないこと、軽いストレッチやマッサージで血流を促すことも青クマ改善のポイントです。
黒クマに効果的な食事と生活習慣
黒クマは、加齢や筋力低下、皮膚のたるみが主な原因です。目の下の皮膚がたるんで影ができることで黒っぽく見えるため、色素沈着や血流だけではなく、ハリや筋肉の衰えを解消する必要があります。
黒クマ対策で重要なのはタンパク質をしっかり摂ること
タンパク質は筋肉や皮膚、コラーゲンの材料になるため、十分な摂取が欠かせません。鶏むね肉、魚、豆腐、納豆、卵など、脂肪が少なく吸収の良い食材を中心に取り入れましょう。
肌の弾力を支えるビタミンCも重要
ビタミンCにはコラーゲン生成を助ける働きがあり、皮膚のハリを保ち、影の原因を減らしてくれます。イチゴやキウイ、パプリカ、柚子、アセロラなどを、毎日の食後デザートに取り入れてみましょう。
黒クマ対策には血行を促進するビタミンEとオメガ3脂肪酸も重要
ビタミンEとオメガ3脂肪酸は、ナッツ類やアーモンド、青魚(サバ・サンマ・イワシなど)を摂ることで、血流が改善し、皮膚に必要な栄養が届きやすくなります。
さらに、体のむくみを防ぐためにカリウムの摂取も意識すると良いでしょう。むくみが減ると皮膚のたるみが目立ちにくくなり、黒クマが軽く見えます。バナナ、アボカド、じゃがいも、ひじきなどに多く含まれています。
黒クマは、目の下の筋肉「眼輪筋」の衰えとも深く関係しています。食事に加えて、目元のトレーニングや表情筋を動かすマッサージを取り入れると、皮膚のたるみを予防できます。
青クマと黒クマ、それぞれに共通する“台所ケア”
青クマも黒クマも、共通して大切なのは血行を整える食事と生活習慣です。
冷たい飲み物を控え、体を温める料理を増やすこと。根菜類やスープ、しょうが、にんにくなど、血流をサポートする「養生食材」を毎日の食卓に少しずつ加えてみましょう。また、油の種類を見直すのも効果的です。酸化しにくいオリーブオイルや亜麻仁油を選ぶことで、体の炎症を抑え、血管の健康を保てます。睡眠前の過食やアルコールの摂りすぎは、翌朝のむくみや血行不良の原因になります。
「食事で整える」「マッサージで巡らせる」「休息で回復させる」この3つをバランスよく続けることが、青クマにも黒クマにも共通する最良の対策です。
週末に試したい、台所からできる目の下のクマ改善レシピ
目の下のクマ対策は「栄養を足すだけ」ではなく、「毎日続けやすい食事」にすることがポイントです。忙しい平日でも無理なく作れるように、簡単で効果的な食材の組み合わせを紹介します。
朝は、温かいスープに鉄分とビタミンCを加えましょう。例えば、ほうれん草とベーコンのスープにレモンを少し絞るだけでも、吸収効率が上がります。夜は、鮭とアボカドのグリルにオリーブオイルをかけて。脂質とビタミンEの組み合わせで血流が整い、肌の修復にも役立ちます。また、間食にはナッツやドライフルーツを。カカオ70%以上のチョコレートも血行促進に良いとされています。
目の下のクマを悪化させる食生活に注意
いくら栄養を摂っても、体に負担をかける習慣が続いていると効果は半減します。冷たい飲み物の取りすぎや、塩分・糖分の過剰摂取には注意が必要です。冷えは血行不良を招き、むくみや青クマの原因になります。夏でも常温の飲み物を選ぶのがおすすめです。また、コンビニ食や外食に偏ると、亜鉛や鉄、ビタミン群が不足しがちになります。週末だけでも、台所で自炊してみると良いでしょう。ほんの少しの手間で体調が整い、クマの改善効果も感じやすくなります。
マッサージと食事を合わせて“巡り”を良くする
食事で栄養を整えたら、マッサージで血行を促すとさらに効果が高まります。目の下をこすらず、指の腹で軽く押すようにするのがコツです。目頭からこめかみへ向かって、ゆっくりと呼吸をしながらマッサージしてみてください。
お風呂上がりに保湿クリームやオイルを使うと滑りが良くなり、摩擦を防げます。また、ツボ押しもおすすめです。目の下の「承泣(しょうきゅう)」やこめかみの「太陽(たいよう)」のツボをやさしく押すと、血行が促されてクマが薄くなりやすくなります。
目の下のクマ対策は「食べる」「休む」「めぐらせる」の3つのバランス
食事はもちろん大切ですが、睡眠と生活リズムも無視できません。寝不足は血流を滞らせるだけでなく、肌の再生サイクルを乱します。理想は1日7時間前後、就寝前1時間はスマートフォンを見ないようにして、体をゆるめる時間を作りましょう。また、ストレスがたまると交感神経が優位になり、血管が収縮して血流が悪化します。ゆったりと深呼吸をしたり、軽くストレッチを取り入れることもクマ対策の一部と考えてください。
健康を維持するための「養生食」とは
最近では「食養生」という考え方が広まっています。
体のバランスを整えることが美しさを保つ基本という考え方で、目の下のクマ改善にも深く関係しています。例えば、体を温めるしょうがやにんにく、疲れをとる黒ごま、血行を促すクコの実など、昔ながらの食材には機能性の高い成分が含まれています。更年期世代の女性は、ホルモンバランスの変化で血行や代謝が落ちやすくなります。和食中心の食事に戻すだけでも、クマ対策としての養生効果を実感できる人が多いです。
コスメやサプリも“内と外の両輪”で考える
「目のクマに効くサプリ」や「ビタミンC誘導体配合のアイクリーム」なども数多く売られています。こうしたコスメは一時的な効果が得られますが、基本は食生活の見直しとセットで使うことが大切です。体の中が整っていないと、外側のケアだけでは持続しません。
自分に合うアイテムを選ぶときは、「信頼できる成分表示」「医師監修」「長く続けやすい価格帯」という3つをチェックすると良いでしょう。
食事で“血と肌のハリ”を作ることが目の下のクマ改善の第一歩
目の下のクマを隠すより、体の中から改善していく、これがクマ対策の考え方です。
マッサージやコスメももちろん効果的ですが、体の内側から整えることが大事です。目の下のクマは「老いのサイン」ではなく、「体からのメッセージ」。忙しい日々の中でも、食事や習慣を少し見直すだけで、肌と心のめぐりはゆっくりと変わっていきます。
食事やマッサージなど、セルフケアだけでなかなか改善できない場合は美容クリニックの施術もおすすめです。
目の下のクマを美容クリニックで改善する
青クマと黒クマは原因がまったく異なるため、美容クリニックで選ばれる治療法も変わります。セルフケアで改善しにくい場合や、早く確実に変化を感じたい時の参考にしてください。
青クマの美容クリニックのおすすめの治療
青クマは血行不良で血管が透けて見えることが主な原因のため、血管の見え方を和らげたり、皮膚に厚みを与えて透け感を抑えたりする施術が中心になります。ヒアルロン酸注入は、薄い皮膚にふくらみを与えて血管が透けにくい状態を作ります。少量で自然な変化を出せるうえにダウンタイムが短く、初めての青クマ治療としてもお勧めの方法です。また、PRP(多血小板血漿)治療は自分の血液から抽出した血小板を注入し、肌の再生力を高めることでハリ不足や薄さを改善する方法で、青クマ特有の透け感や質感をケアしたい人に向いています。
黒クマの美容クリニックのおすすめの治療
黒クマの治療は“影を生まなくする”ことに重点が置かれます。
脱脂(経結膜脱脂術)で、下まぶたの裏側から膨らんだ眼窩脂肪を取り除く方法があります。皮膚の表面に傷ができないため仕上がりが自然で、影の原因そのものにアプローチできる治療です。また、ハムラ法・裏ハムラ法では余っている脂肪をただ取るのではなく、へこんだ部分に移動させてなじませることで、膨らみとへこみの両方を整えます。黒クマの複合的な悩みに適した、より立体感を意識した治療です。ダウンタイムがほとんどなく、手軽に受けやすいヒアルロン酸注入は、へこみ部分をふくらませることで影を柔らかくし、切らずに改善を目指すこともできます。切る治療を避けたい方は、HIFU(ハイフ)を使って深部から引き締める方法もあります。
目の下のクマやくぼみを治す方法は一つではありません。目の下のクマの症状は自己判断が難しいことがあるため、専門のクリニックで医師の診察を受けることをお勧めします。
施術を受ける前には、費用やダウンタイム、副作用やリスク、メリットについて、医師と納得できるまで相談し、慎重に医師、クリニックを選ぶようにしましょう。